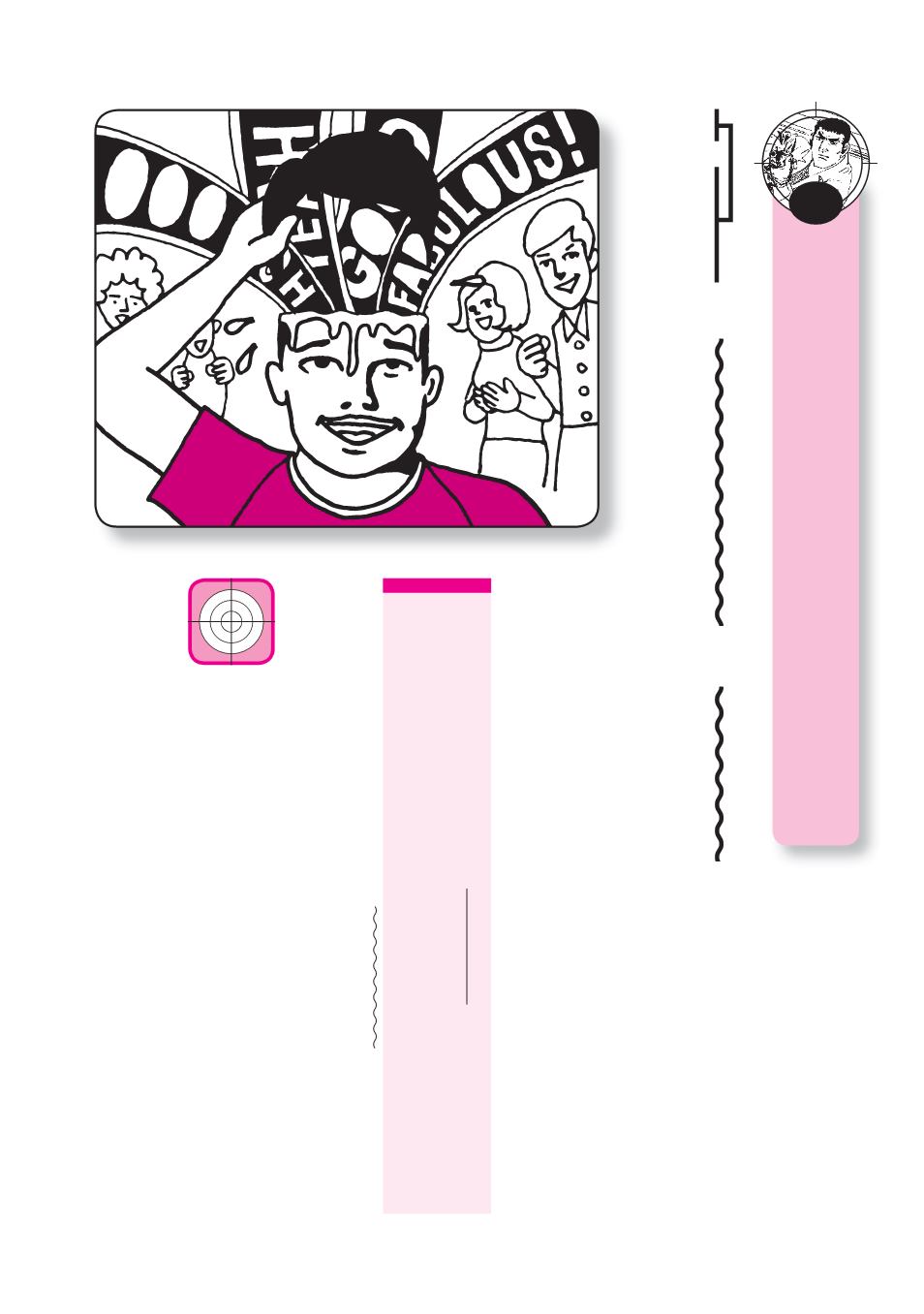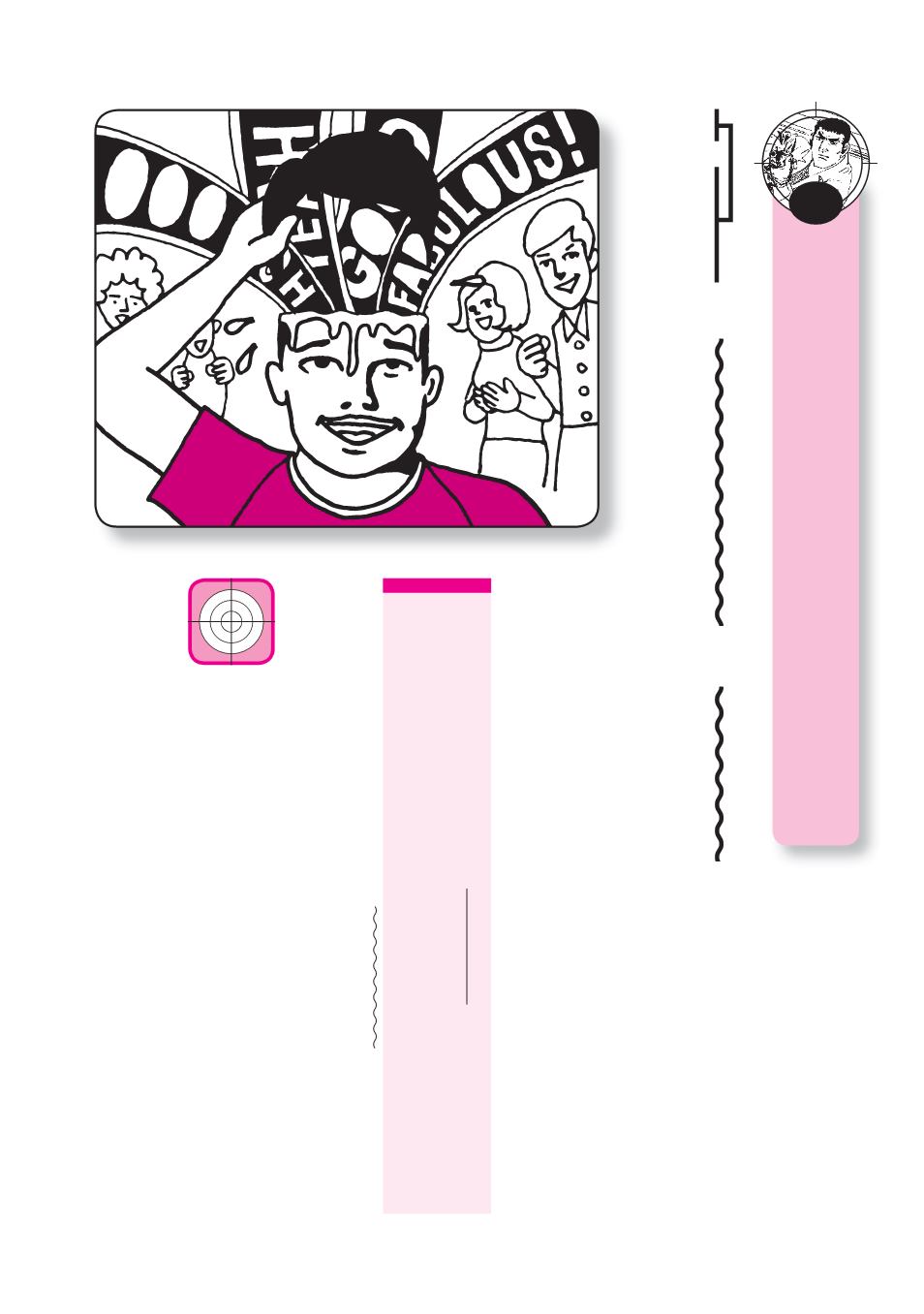
い
ろ
は
-
186
-
「罵る」と漢字をあてる。現代語の
しく言う」ことであるが、これは中世
周囲を気にせず大声をたてる
1
の意。
2
・
3
の意味にも注意。
……と詠む時に、帝、ののしりあはれが
て、御しほたれ給ふ。
(大和)
=
……と詠んだ きに、帝は
大声をたてて
深い感心のさま
をお示しになって、しみじみと涙を流しなさる。
古代においては、言葉には人の心を動かす何かが宿っ
ているものと う、いわゆる「言
こと
霊
だま
信仰」があった。
特に和歌は人の心を動かすものとして尊重された(紀
貫之が『古今和歌集』の「仮名序」でそう述べたのは
有名) 。今で言うメールのやり取りが、昔の和歌のや
り取りにあたるのかな。
1
大声で
。
2
盛んに評
。
3
今を時めく
脳の汁が
大声たて
と
大評判
のの
(動・ラ
【罵る】
133
文 法