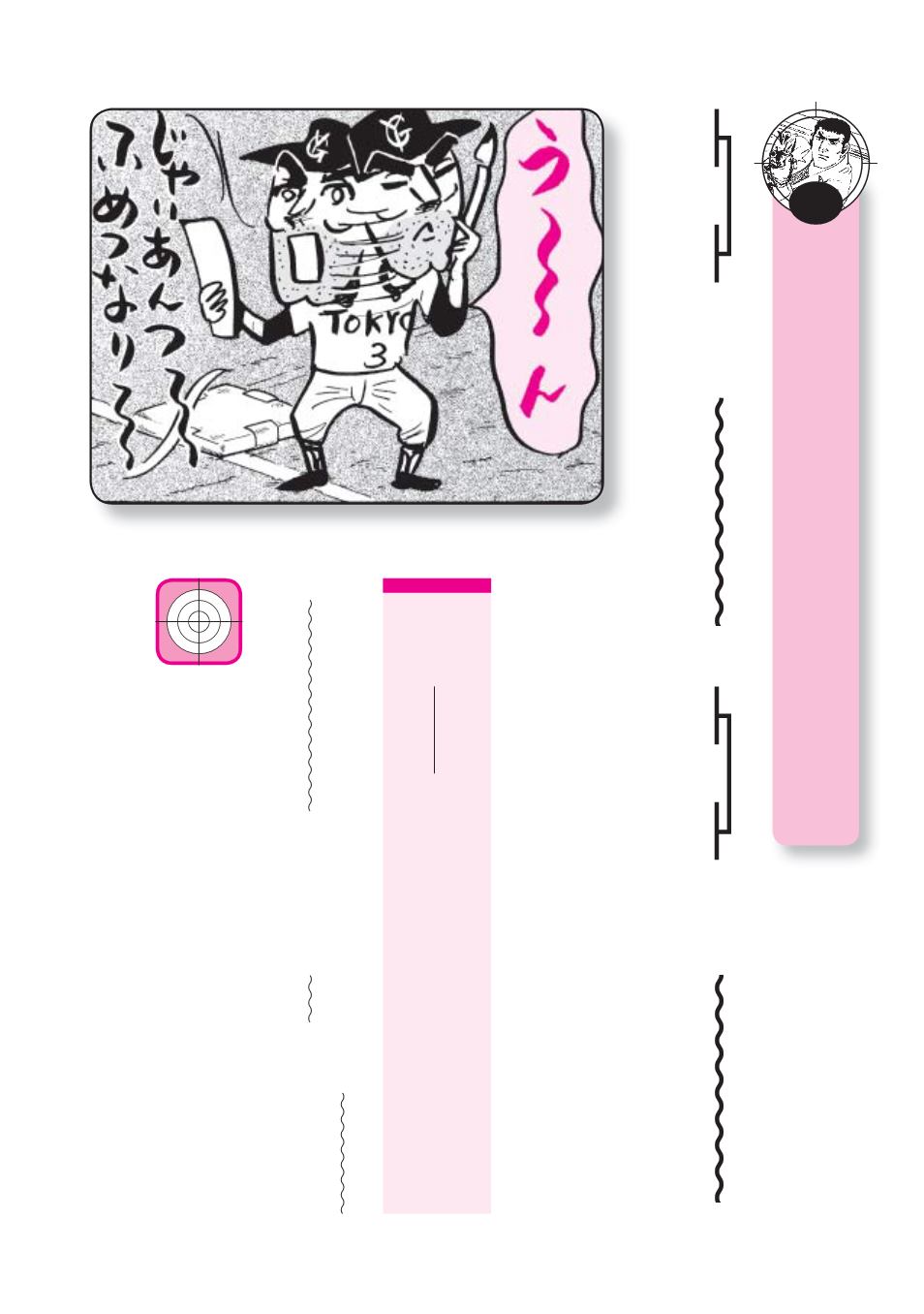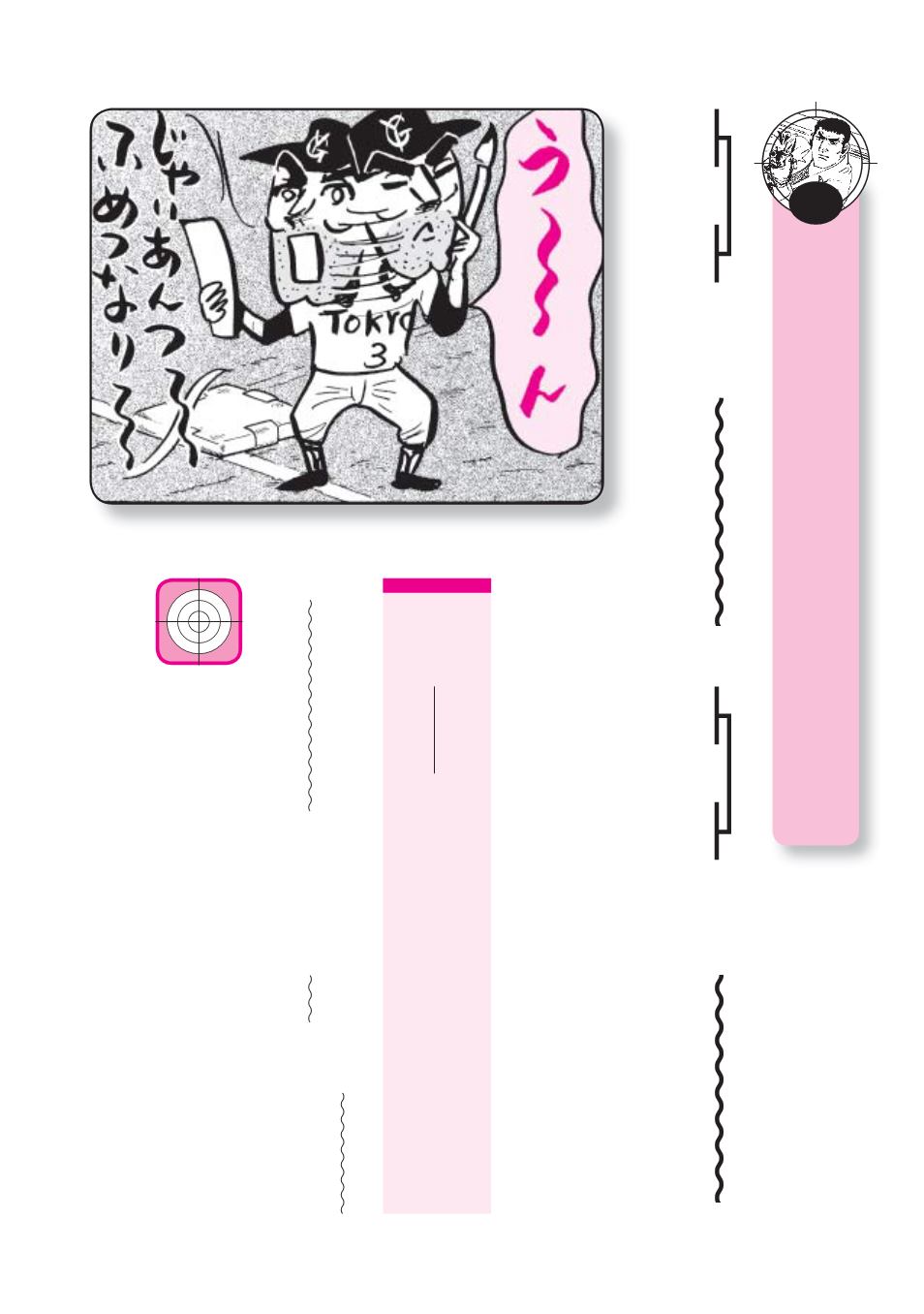
い
ろ
は
-
172
-
1
の 「ながむ」 は 「眺む」 と漢字を
雨」に掛けて用いられる。また
2
の「ながむ」は「詠む」と漢
字をあて、
1
の「ながむ」と掛詞で用いられる。
夕
ゆう
月
づく
夜
よ
のをかしき程に、 出
い
だしたてさせ給ひて、
やがてながめおはします。
(源氏)
=
夕方の月の趣深いころに (靫負の命婦を桐壺の更衣
へ)出発させなさって、 (桐壺帝は)そのまま
物思いにふ
けりながらぼんやり
(夕月などを)
見て
いらっしゃる。
「させ/給ひ」の「させ」はここでは使役の助動詞。 「せ
/給ふ・させ/給ふ・しめ/給ふ」の形のときは「尊
敬+尊敬」 = 「〜なさる」 の場合が多いが、
「使役+尊敬」
=「〜させなさる」のときもある で注意が必要だ。
1
(眺む
物思い
やりと見
。
2
(詠む)
詩歌を節をつ
ずさむ
。吟じる。
長嶋無理
もの思う
、長嶋無
歌を詠む
なが
(動・マ 【眺む】 【
123
文 法