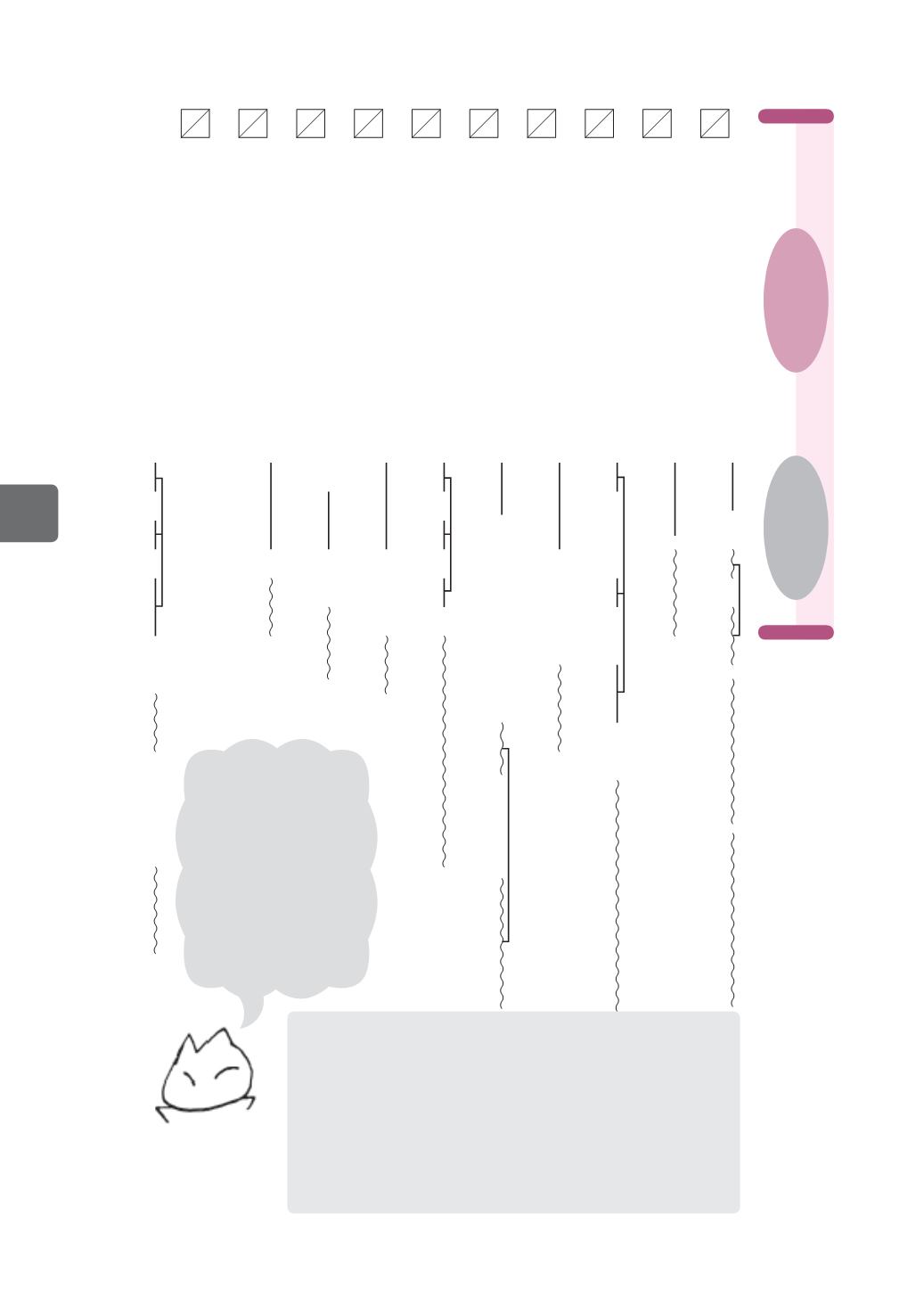古文単語565 赤版 - page 143
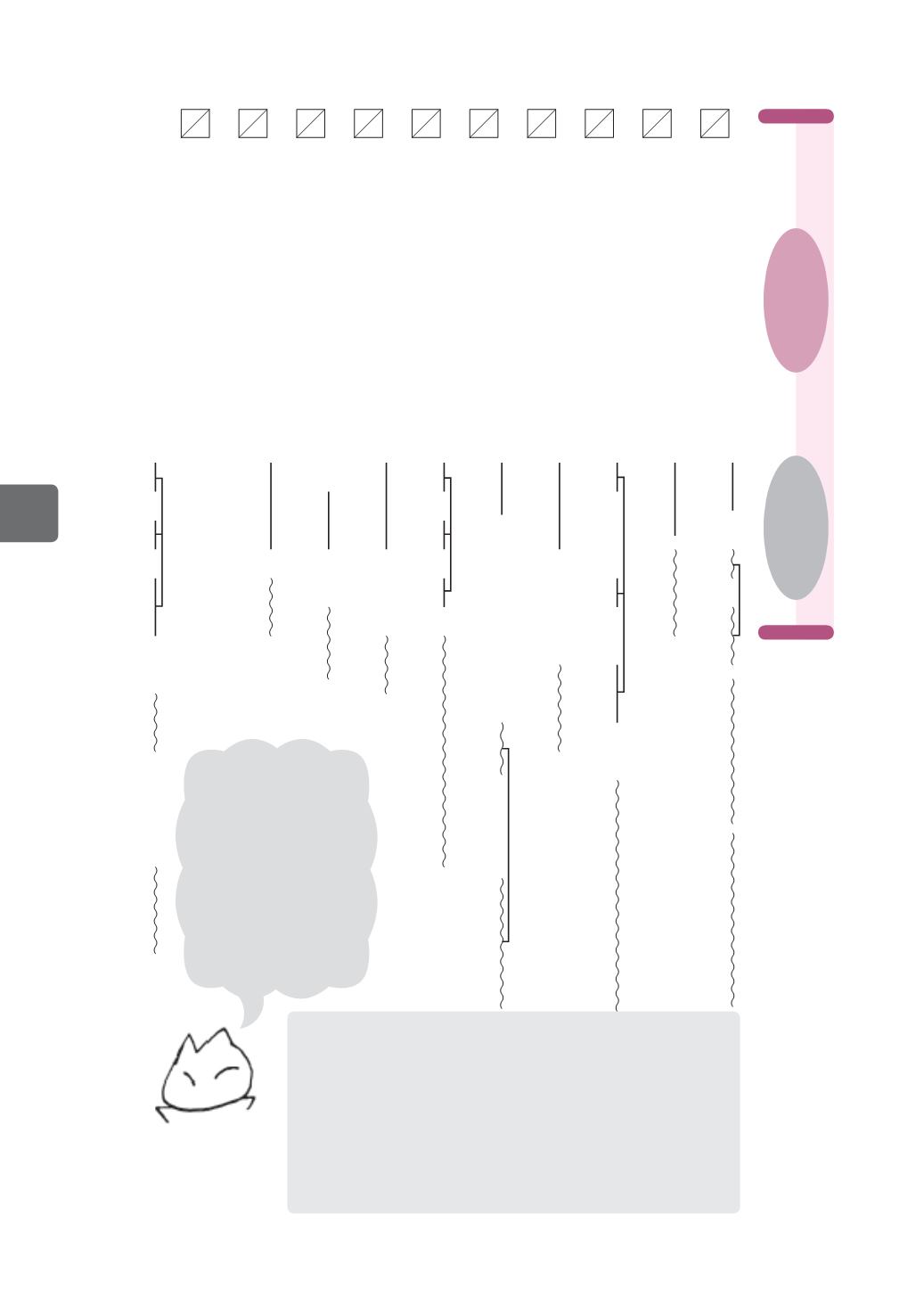
-
143
-
301
A
すずろ (なり)
……
鈴六個
や
っ
たら
、
なんとなく
思いがけない
302
C
すだく
………………
須田君
集まる
303
A
ずちなし
……………
ずーっとチューなしでは
どうしようもない
304
A
すなは
………
砂は血だらけ、
すぐに
110番
305
C
ずは
……………………
ズバッと言わないで、
もし
言いたく
ないならば
306
C
すべなし
……………
すけべな梨、
どうしようもない
307
C
すまふ
………………
すもう取り、
争う
308
C
すゑ (末)
……………
♥
吸えー、
下
下の句
の口
309
C
ずんず (誦ず
……
ずんずん
読む
310
A
せうそこ ・ せうそく (消息)
…
セイウチそこそこ
手紙
を書いて
訪れる
ゴロ
302
「すだく」は「集く」
と漢字をあてる。
305
「ず
は」は連語で打消「ず」
に係助詞「は」の付いた
もの。中世には 「ずんば」 、
近世には「ずば」となり、
「もし〜ないならば」の意
で用いられた。
307
「すまふ」
は「争ふ(=争う) 」以外
にも「辞ふ(=辞退する) 」
があるので注意。
308
「す
ゑ」は和歌の下の句
七七)のことで、上の句
(=五七五) は 「もと (本) 」
と言う。
309
「ずんず」は
「じゅす・ずず・ずす・ず
うず」 も言う。 「 (詩歌 ・
お経などを)声を出して
よむ」こと。サ変動詞。
●CD
Tr a c
35
本 (もと) =上の句
=五七五
末 (すゑ) =下の句
=七七
和歌
�︷�
①
②
③
さ
①
②
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153
133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...298