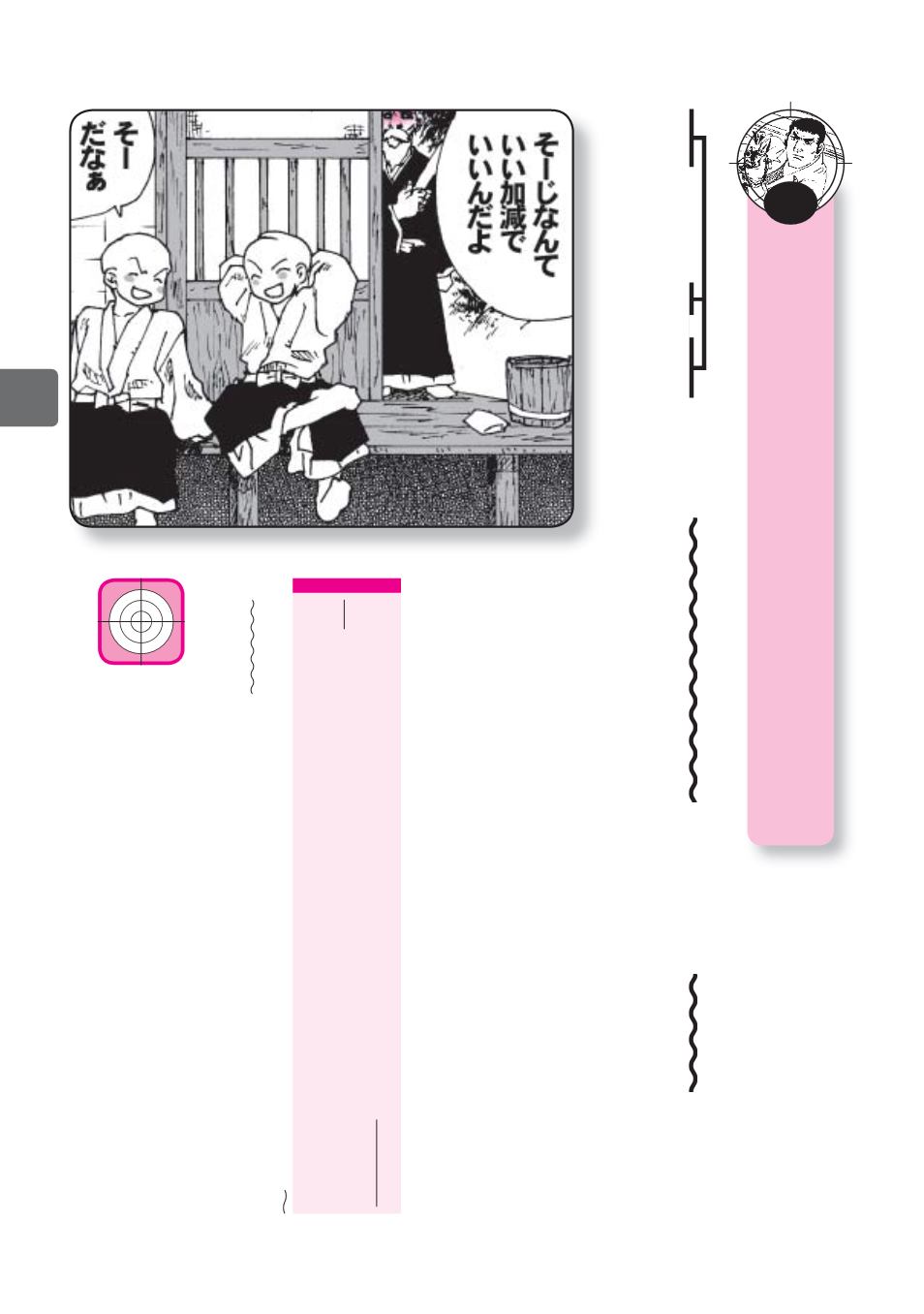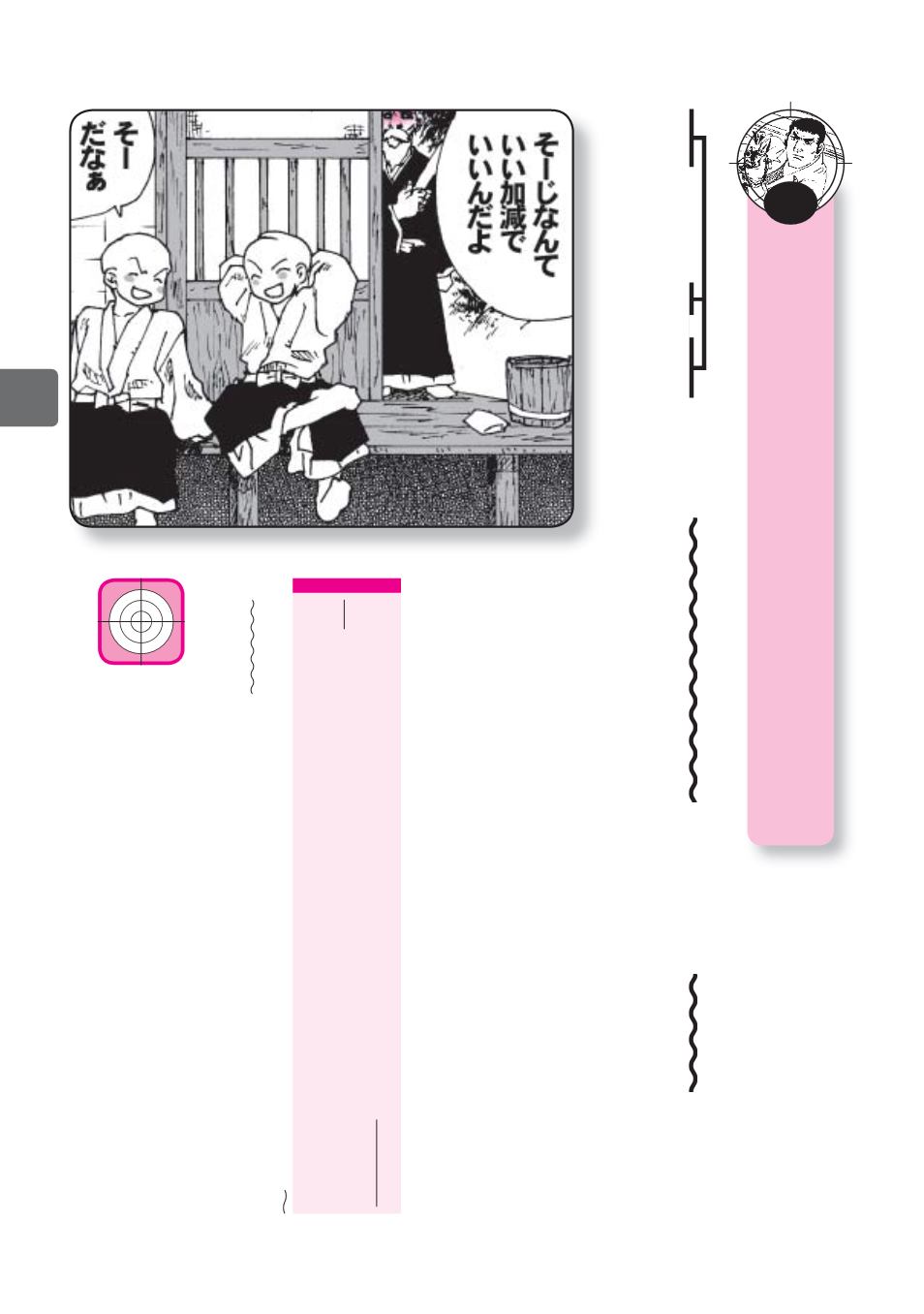
-
81
-
い
ろ
は
「疎かなり・愚かなり」と漢字をあて
くないさまに用いるが、 古語では
1
の意味が多い。
3
の場合、
「〜
とはおろかなり」 「〜ともおろかなり」 「
かなり」
「〜といへばおろかなり」などの形で
という意味になる。
わづかに二つの矢、師の前にてひとつをおろか
にせんと思はんや。
(徒然)
=
たった二本の矢なのだから、師匠 で、先に射る矢を
い
い加減に
しようと思うだろうか、いや思わないだろう。
「にて」は一語の格助詞。 「せ/ん」の「ん」は意志。
文末の「や」は反語「〜だろうか、いや〜ない」 。終
助詞的用法なので結びはない。
1
いいかげ
。おろそ
2
未熟だ
。劣る。
3
言い尽くせな
オー、廊下
いいかげん
、この
未熟
者!
おろ
(形動・ナ
【疎かなり・
55
文 法
あ