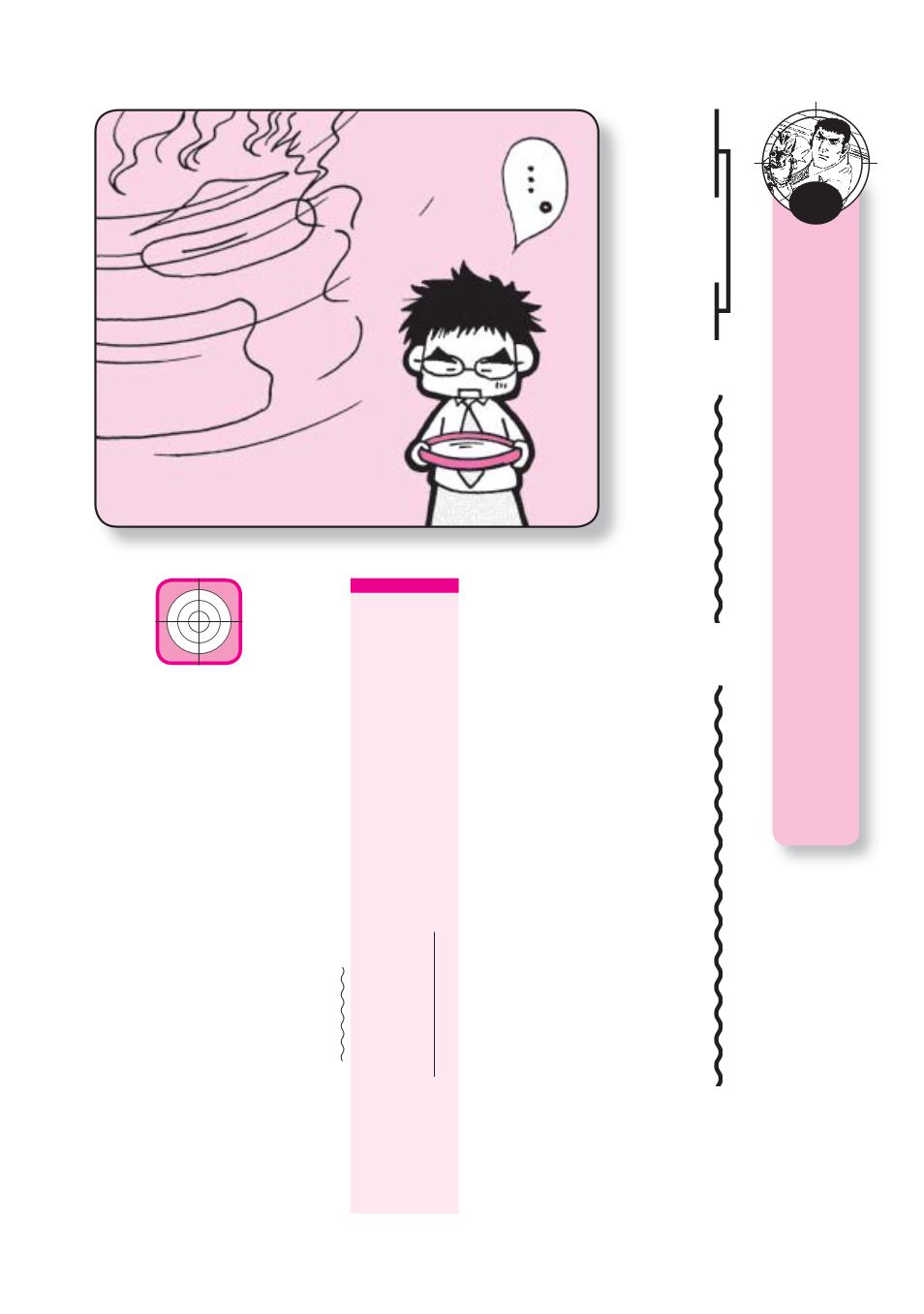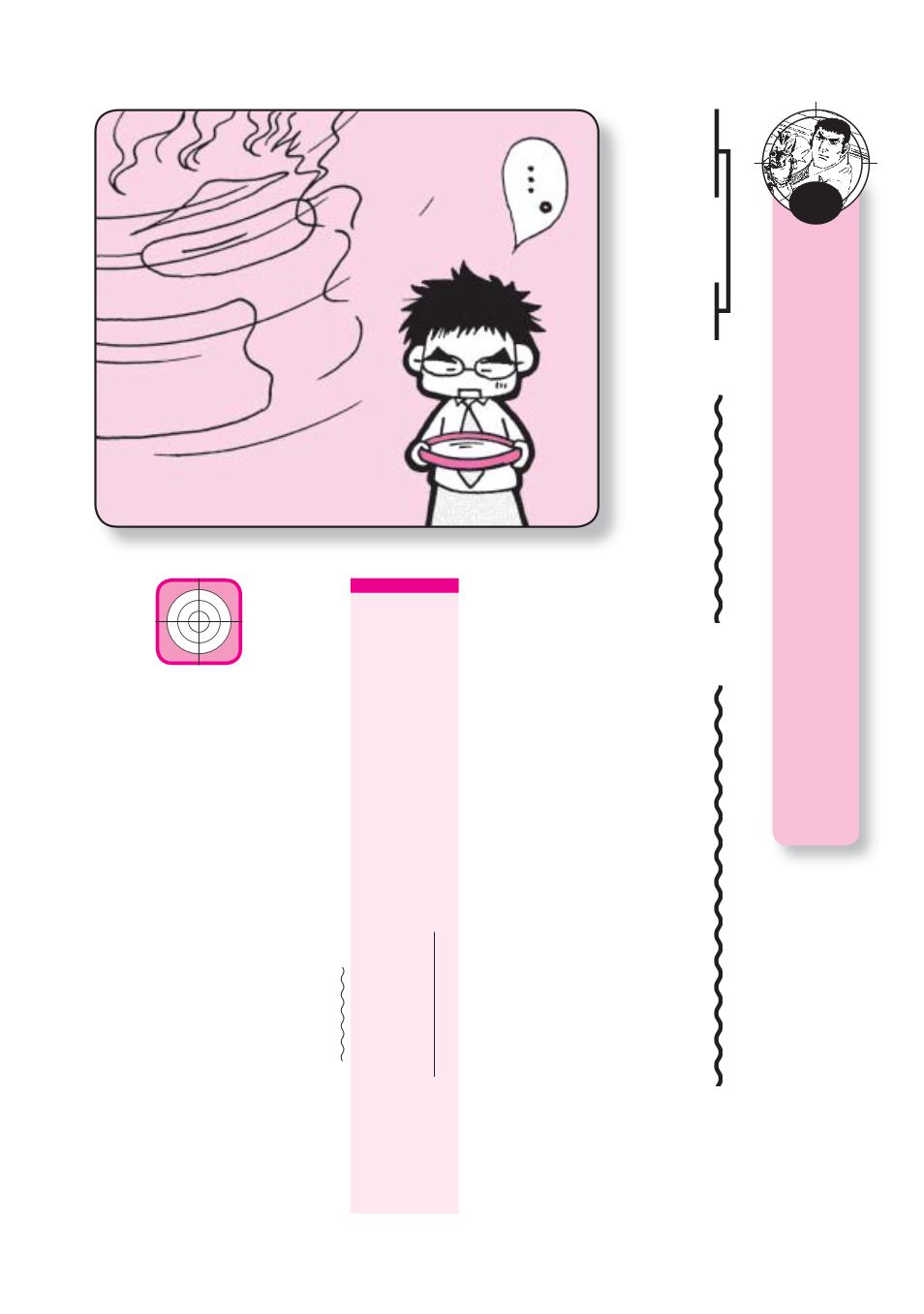
い
ろ
は
-
78
-
「覚ゆ」と漢字をあてる。 「思ふ
自発の助動詞「ゆ」がついた「おもは
て、さらに「おぼゆ」となったもの。
1
・
2
の意味も大切だが、
特に
3
の意味に注意。
尼君の見上げたるに、 少しおぼえたる所あ
子なめりと見給ふ。
(源氏)
=
尼君が女の子を 上げた顔 、 少し
似ている
所があるので、
尼君の子であるらしいと源氏はご覧になる。
「な/めり」=断定の助動詞「なり」の連体形「なる」
の撥音便「なん」の「ん」の無表記形+推定の助動詞
「めり」の終止形。 「な」が入試で問われた場合、解答
は 「断定の助動詞 「なり」 の連体形 (の撥音便の無表記) 」
となる。 「なるめり↓なんめり↓なめり」と変化した
1
自然に
。
2
思い出さ
3
似て る
。
お盆の湯
似ている
と
自然に思
おぼ
(動・ヤ
【覚ゆ】
52
文 法