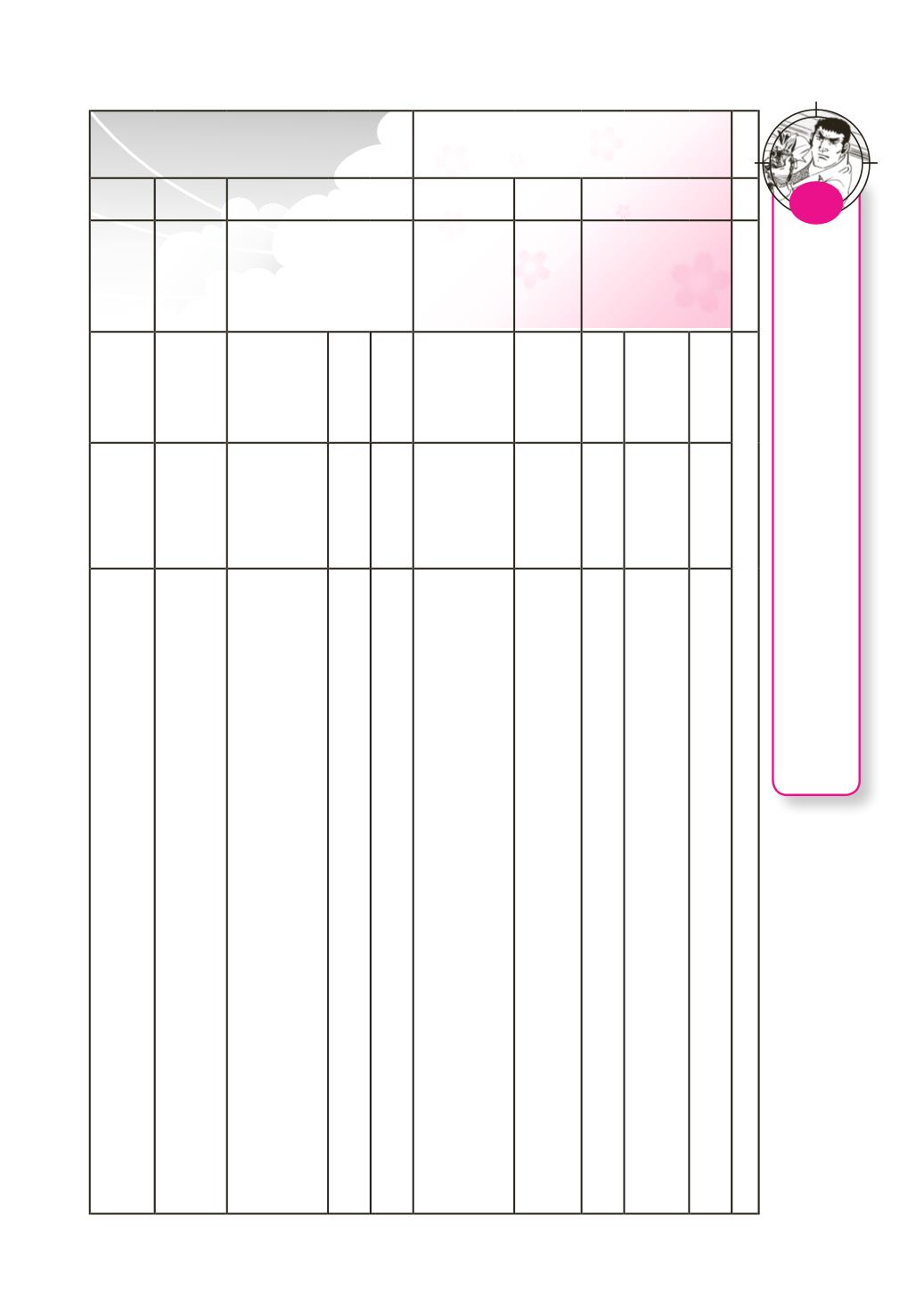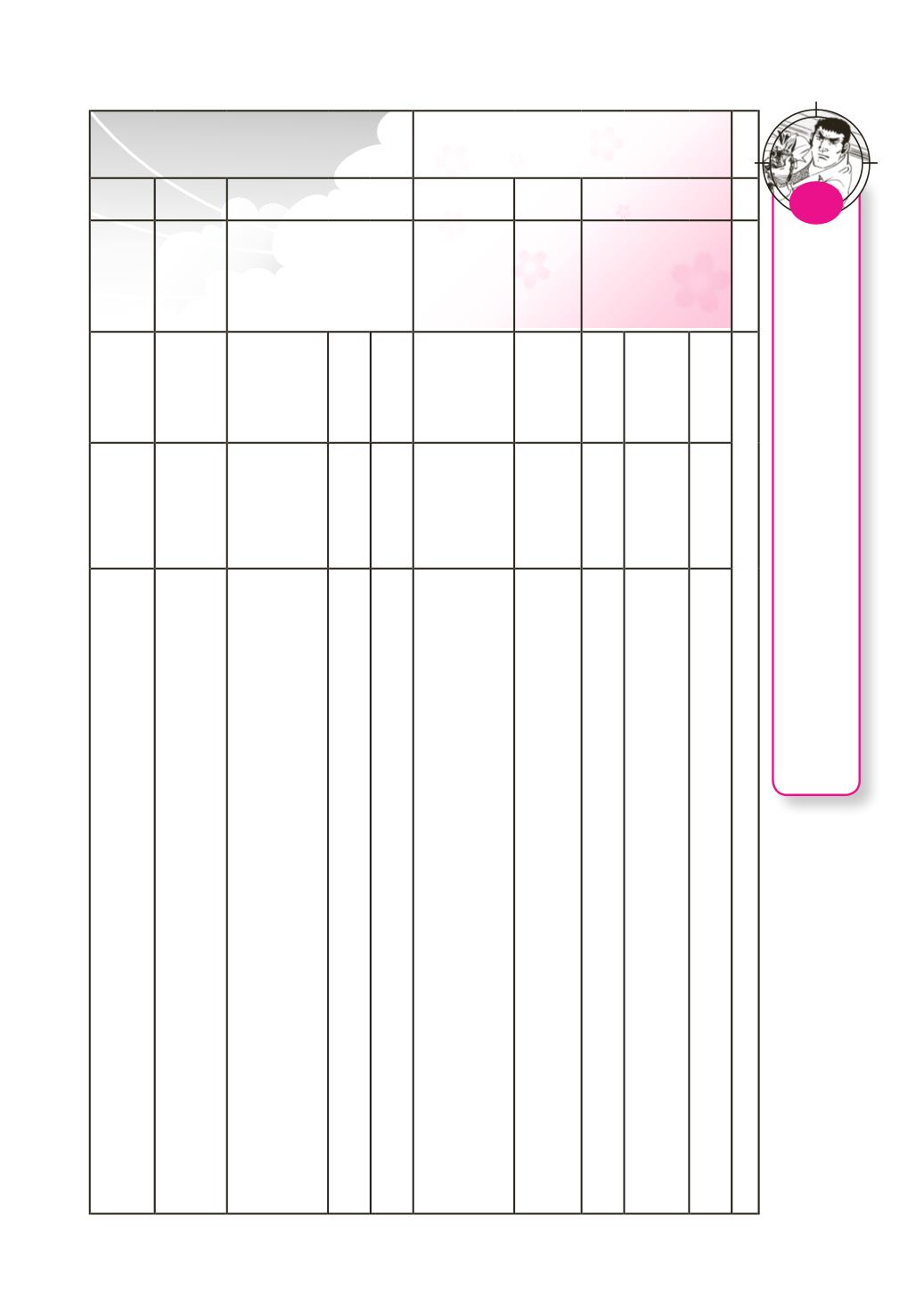
古
典
常
識
-
262
-
月の
季節
月
異名
年中行事
春
一月
睦
む
つ
き
月
一日
四
し
方
ほう
拝
はい
天皇が
清
せい
涼
りょう
殿
でん
東庭で四方の神霊を
七日
白
あお
馬
うまの
節
せち
会
え
宮中にひかせてきた青馬
に宴を賜る。青は春の色で、
邪
じゃ
気
き
祓
ばら
いになる。
十一日頃
県
あがた
召
めしの
除
じ
目
もく
春の除目。地方官 (外官) であ
国
くにの
守
かみ
受
ず
領
りょう
を任命する。
二月
如
き さ ら ぎ
月
十五日
涅
ね
槃
はん
会
え
釈迦がすべての煩悩を滅し 入寂した
法
ほう
会
え
を行う。
三月
弥
や
よ
い
生
三日
上
じょう
巳
し
五節句の一つ。川辺で宴を張り、水に浮か
杯
さかずき
が自分の前を過
ぎる前に詩歌を作る。民間では
流
なが
し
雛
びな
が行われ、江戸時代以降、
女子の成
長を祈る
雛
ひな
祭
まつ
りとして定着した。
夏
四月
卯
う
月
づ き
一日
衣
ころも
更
が
え
装束・調度を夏物に改める。
八日
灌
かん
仏
ぶつ
会
え
釈迦降誕の日の法会。釈尊像に甘茶を注ぐ。
中の酉の日
賀
か
茂
も
の祭り
古典で 「祭り」 といえばこの祭り。賀茂神社の祭りで、
双
ふた
葉
ば
葵
あおい
を飾
るので 「葵祭り」 、
石
いわ
清
し
水
みず
八
はち
幡
まん
宮
ぐう
の祭礼 「南祭り」 に対して、
「北祭り」
ともいう。一八八四年以降は五月十五日 行われ
五月
皐
さ
月
つ き
五日
端
たん
午
ご
五節句の一つ。邪気祓いの菖蒲を軒に飾る。尚武に通じることから
のちに男子の成長を祈る節句。
六月
水
み
無
な
月
づ き
晦日
大
おお
祓
はらえ
水
み
無
な
月
づき
祓
ばらえ
・
夏
な
越
ごしの
祓
はらえ
とも。半年間の汚れを祓うみそぎ。
2